コンテナハウスのデメリットとは?事前に理解すべき7つのポイント!


村上悠です。
自宅、賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てるなど、家づくり経験があります。
さらに、経営する複数の賃貸物件のリフォームを何度も行ったことがあります。
その経験をベースに記事を書こうと思います。
今回は、コンテナハウスのデメリットについて、詳細に解説します。
ここ数年、街でもよく見かけると思いますが、コンテナハウスが増えました。
美容院、ショップ、カフェ、ホテル・・等、斬新なデザインでおしゃれなコンテナハウスが、本当に多いです。
次の記事で、コンテナハウスのおしゃれさについて解説していますので、こちらも併せてお読みください。
そんなコンテナハウスで、自宅を建てたいという方も、最近、増えかなり注目されています。
確かにコンテナハウスは、通常の家では表現できない、斬新でおしゃれな建物です。
しかし、良いイメージだけで、コンテナハウスを建てるのは、極めて危険です。
せっかくコンテナハウスを新築しても、こんなはずではなかった失敗したと、後悔することにもなりかねません。
ぜひ、コンテナハウスの良い面だけでなくデメリットもよく理解した上で、家づくりを進めてください。
本記事では、7つのデメリットについて徹底解説しますので、ぜひ後悔しないためにも、お読み頂ければと思います。

もし、あなたが、コンテナハウスを検討されていて、以下の4つの内一つでも該当するのであれば、ぜひ、最後までお読み頂ければと思います。
- 家づくりを何からスタートしていいのか、よくわからない。
- 住宅展示場に行きたいが、その後の営業が気になって、なかなか行けてない。
- そもそも、コンテナハウスを見学するのにどこの住宅展示場に行けばいいのか、よくわからない。
- 実際に住宅展示場に行ってみたが、特に役に立ちそうな情報は得られなかった。
![]()
- 今は、わざわざ住宅展示場に行かなくても、コンテナハスについても家づくりに必要な情報を集めることができます。
- 当然ですが、住宅展示場に行けば、住宅メーカーさんから営業を受けることになります。
- どこの住宅メーカーに依頼するか何も決まっていない段階で、具体的な話をするのは、抵抗があります。
![]()

そこで、あなたにご紹介したいサービスがあります。
家づくりに役立つ情報を、短時間に効率良く、確実に集めることができる「タウンライフ家づくり」です。
「タウンライフ家づくり」の一括依頼サービス:
- あなたが希望する複数の住宅メーカー(ハウスメーカー・工務店)から、あなたに合ったオリジナルの「間取りプラン・見積り」を無料で送ってもらうことができます。
- 様々な大手ハウスメーカーのカタログも、無料で送ってもらうことができます。(住宅展示場に行く必要がありません。)
- 約3分で、全て無料でネットで一括申請できます。

↓ ↓
![]()

住宅展示場に行かず、まずは「タウンライフ家づくり」のサービスで情報収集するのが賢い選択です。
- あなたは、ご自分の要望を取り入れたオリジナルの間取りプランを無料で入手できます。
- 住宅メーカー各社の間取りプラン、見積もりを比較できるので、結果、あなたは、大幅に安く家を建てることが可能です。
- あなたが希望するのであれば、エリアの優良土地を提案してもらえます。
- あなたは、今すぐに、家づくりをスタートできます。
コンテナハウスで失敗しないためにはどうすべきか?


まずは、コンテナハウスを新築した後に、失敗したと後悔しないためには、どうすべきかを解説したいと思います。
コンテナハウスをお考えの方は、ぜひ、しっかり理解するようにしてください。
コンテナハウスは、次の記事をお読み頂ければ、よくおわかり頂けると思いますが、おしゃれで、本当に素敵な建物です。
なぜ、ここまで注目され人気なのか、その理由がよくわかるはずです。
しかし、その反面、せっかくコンテナハウスを新築した後に、こんなはずではなかった、失敗だったと後悔される方も、一定数いらっしゃいます。
なぜ、失敗したと後悔することになってしまったのか?
それは、コンテナハウスが一体どういうものなのか、しっかり理解しないまま、いいイメージだけで進めたからです。
例えば、よくあるのですが、コンテナハウスを安い価格で建てられると勘違いしている方です。
コンテナの本体価格から、勝手にイメージして、安く手軽に、建てられると思い込み、家づくりを進める方です。
次の記事で、コンテナハウスの価格について詳細に解説していますが、全く、そのような事はありません。
価格について理解せず、安いというイメージだけで進め、その結果、資金不足となり、満足できる家を建てることができなかったと後悔されるパターンです。
コンテナハウスで失敗しないためには、コンテナハウスのメリットだけでなく、デメリットについても、事前にしっかり理解することが重要です。
ぜひ、コンテナハウスのメリット、デメリットを、充分に理解した上で、家づくりを進めてください。
コンテナハウスの7つのデメリットとは?
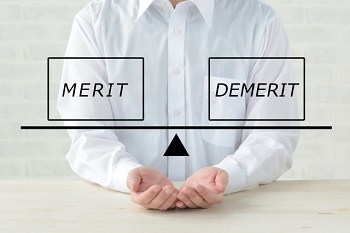

それでは本題です。
コンテナハウスの7つのデメリットについて解説します。
よく、ここを勘違いされている方が多いので、注意するようお願いします。
これからお話する7つのデメリットですが、(3)(4)(6)(7)は、コンテナハウスならではの特有のデメリットであり、その他の(1)(2)(5)は、一般の住宅と同じデメリットです。
それでは順々に説明をしていきます。
- 価格は安くない
- 移動が大変
- 立地場所が限定
- 天井が低い
- 固定資産税が課税
- 断熱処理が必要
- 防水対策が必要
価格は安くない
それでは、1つ目のコンテナハウスのデメリットについて解説します。
コンテナハウスは、決して安く手軽に建てられるものではないというデメリットです。
確かに昔は、中古の安いISO海洋輸送用コンテナを使用して、安くコンテナハウスを建てることができた時代もありました。
しかし、現在では、厳しい建築基準法をクリアする必要があるため、そのような安価なコンテナを使って建てることができません。
建築基準法に適合した建築用コンテナで建てる必要があります。
また、コンテナハウスは、通常の注文住宅と同じで、希望の間取りや内装・設備、外装を決めなければ、正確な金額はわかりません。
当然、基礎工事、水道・ガス・電気のライフラインの工事が必要ですし、外壁に貼る建材や、内壁費用も必要です。
キッチン、トイレ、風呂等の水回りはオプションになるため、グレード次第で、価格は大きく異なってきます。
このように、コンテナハウスも通常の住宅と同じように価格は高く、総額では、木造建築と同等か少し高い金額でないと建てることができません。
コンテナハウスの価格については、次の記事で詳細を解説しておりますので、ぜひ、併せてお読み頂ければと思います。
移動が大変
2つ目のデメリットは、コンテナハウスを簡単に移動させることができないというデメリットです。
コンテナは物流で使わるものであるため、コンテナハウスも何となく簡単に移動ができるイメージがあるようです。
また、コンテナハウスをトレーラーハウスのように簡単に移動ができると勘違いされている方も、結構いらっしゃいます。
コンテナハウスは、いったん設置してしまったものは簡単には移動できません。
移動するには、建物を基礎から外し、ライフラインを全て外し、運べる状態に分解し、移動することになるので、かなり大変です。
仮にコンテナ1台程度の小規模なコンテナハウスであっても、移動させるとなると同じです。
そして、移動先では、基礎工事をし直し、再度組み立ててライフラインの整備をする必要があるので、費用もかかるし、手間もかかります。
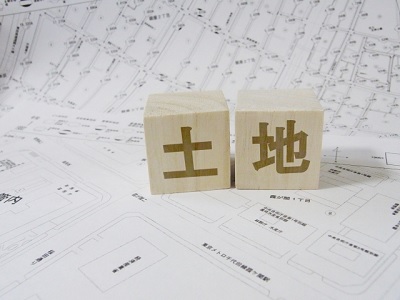
立地場所が限定
3つ目は、コンテナハウス特有のデメリットで立地場所が限定されることです。
コンテナハスは、コンテナを使った建物です。
そのコンテナは、既に躯体として完成しているものであり、そのままの形で運んで設置するものです。
コンテナは主に20フィート、40フィートのものなので、この大きさのコンテナを運び込める道路、立地が必要です。
設置場所まで搬入経路、コンテナを積載した大型トラックが通れる道かどうか、さらに、設置場所において、上の画像のように、コンテナを吊り上げる大きなクレーンが使えるかどうかの確認が必要です。
具体的には、道幅が4.5m以上の道路であって、電線や高さのある障害物がないかどうかがチェックポイントです。
設置場所に隣接する道路が狭ければ、トラックが通れず、コンテナを運びこむことができないので、コンテナハウスを建てることができません。
プレハブ住宅のようにパーツとして運んで、現地でコンテナに組み上げるとしても、別途費用がかなりかかります。
天井が低い
4つ目は、コンテナハウス特有のデメリットで天井が低いことです。
通常の規格コンテナのサイズは、天井の高さが約2.5mで、そこに断熱材を入れると、天井高は2.1m~2.2mと低くなってしまいます。
一般住宅の天井高に比べると少し低く、圧迫感を感じるかもしれません。
ただ、高さが2.6m~2.7m程あるハイキューブのコンテナを使えば問題ありませんが、規格外のものなので、当然、費用は高くなります。
規格外サイズのコンテナを輸入する場合は、輸送費も高くなります。

固定資産税が課税
5つ目は、コンテナハウスに対する固定資産税の課税のデメリットです。
コンテナハウスをトレーラーハウスと混同し、固定資産税の課税対象ではないと勘違いされる方がいますが、それは間違いです。
コンテナハスは、屋根があって四方を壁で囲まれており、構造部を固定して地面に接着させるため、建築物とみなされ固定資産税が課税されます。
税金は、資産の評価額×1.4%で計算されます。
ここは、次の記事で詳細に解説しておりますので、併せてお読み頂ければと思います。
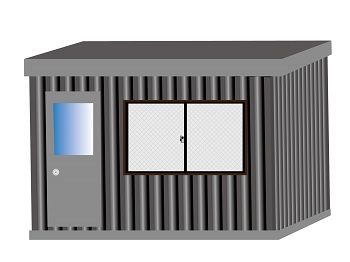
断熱処理が必要
6つ目は、コンテナハウス特有のでメリットですが、断熱処理が必要なことです。
コンテナは、鉄でできていますので、当然、熱すると熱くなります。
木造住宅等と比べ、鉄製のコンテナは断熱性能が低く、熱がこもりやすいため、断熱処理は必須です。
夏は、コンテナ内は強烈に暑く蒸し風呂状態となり、まず住める状態ではありません。
居住用のコンテナハウスは、天井や内壁に断熱材を使用し、外壁に断熱性のサイディングを使用したりする等、断熱処理が必要です。
断熱処理をすれば、コンテナハウスは、一般住宅と違いはなく、暑い夏でも快適に住めます。
あくまでも「コンテナをそのままの状態にした場合」を前提ですが、コンテナハウスのデメリットです。
防水処理が必要
7つ目も、コンテナハウス特有のデメリットですが、防水処理が必要なことです。
コンテナは鉄できていますので、当然、錆びる可能性が高く経年劣化しやすい特性があります。
コンテナハウスは、屋根がフラットであるため水捌けが悪く、屋根部が錆で腐食し、そこから雨漏りする可能性もあります。
そのため、コンテナハウスには、防水処理が必要です。
適切な防水処理を行えば、一般住宅と何ら変わりません。
こちらも、あくまでも「コンテナをそのままの状態にした場合」を前提ですが、コンテナハウスのデメリットです。
まとめ
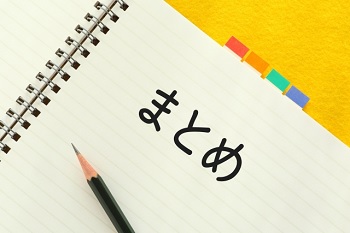

以上、コンテナハウスの7つのデメリットについて解説しました。
参考になりましたでしょうか?
本記事で解説した次の7つのデメリットは、どれも極めて重要なポイントです。
- 価格は安くない
- 移動が大変
- 立地場所が限定
- 天井が低い
- 固定資産税が課税
- 断熱処理が必要
- 防水対策が必要
ここは、しっかり理解した上で、コンテナハウスの家づくりを検討するようにして下さい。
曖昧なまま進めた場合、最悪、こんなはずではなかった、失敗したと後悔することにもなるので、本当にご注意ください。
コンテナハウスには、デメリットもありますが、メリットも沢山あります。
アイディア次第で、何倍もおしゃれでインパクトあるものを建てることができます。
ぜひ、コンテナハウスのデメリットも含め全てをしっかり理解した上で、あなたの家づくりに、このコンテナハウスを検討されては、いかがでしょうか。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ぜひ、あなたの家づくりを成功させてください。
【PR】
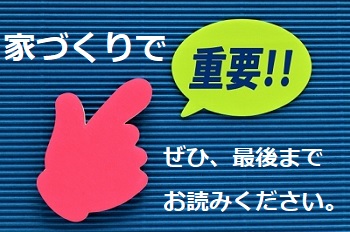

もし、あなたが、コンテナハウスを検討されていて、以下の4つの内一つでも該当するのであれば、ぜひ、最後までお読み頂ければと思います。
- 家づくりを何からスタートしていいのか、よくわからない。
- 住宅展示場に行きたいが、その後の営業が気になって、なかなか行けてない。
- そもそも、コンテナハウスを見学するのにどこの住宅展示場に行けばいいのか、よくわからない。
- 実際に住宅展示場に行ってみたが、特に役に立ちそうな情報は得られなかった。
![]()
- 今は、わざわざ住宅展示場に行かなくても、コンテナハスについても家づくりに必要な情報を集めることができます。
- 当然ですが、住宅展示場に行けば、住宅メーカーさんから営業を受けることになります。
- どこの住宅メーカーに依頼するか何も決まっていない段階で、具体的な話をするのは、抵抗があります。
![]()

そこで、あなたにご紹介したいサービスがあります。
家づくりに役立つ情報を、短時間に効率良く、確実に集めることができる「タウンライフ家づくり」です。
「タウンライフ家づくり」の一括依頼サービス:
- あなたが希望する複数の住宅メーカー(ハウスメーカー・工務店)から、あなたに合ったオリジナルの「間取りプラン・見積り」を無料で送ってもらうことができます。
- 様々な大手ハウスメーカーのカタログも、無料で送ってもらうことができます。(住宅展示場に行く必要がありません。)
- 約3分で、全て無料でネットで一括申請できます。

↓ ↓
![]()

住宅展示場に行かず、まずは「タウンライフ家づくり」のサービスで情報収集するのが賢い選択です。
- あなたは、ご自分の要望を取り入れたオリジナルの間取りプランを無料で入手できます。
- 住宅メーカー各社の間取りプラン、見積もりを比較できるので、結果、あなたは、大幅に安く家を建てることが可能です。
- あなたが希望するのであれば、エリアの優良土地を提案してもらえます。
- あなたは、今すぐに、家づくりをスタートできます。

著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表
自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験があります。
さらに、複数の賃貸物件についても、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
そういった家づくり、リフォーム経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。
家づくり、リフォーム等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。







